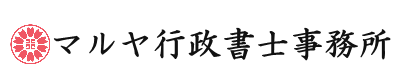1,配置技術者の要件
建設業者様の中には、専任技術者(専技)のことを現場監督や施工責任者といった施工現場で仕事をする技術者と思っておられる方がいらっしゃいます。
実は、専任技術者(専技)は、施工現場で仕事をされる技術者ではなく、あくまでも営業所のみで仕事をされている技術者なのです。
原則として、専任技術者(専技)は施工現場で管理的立場の技術者になることはできません。
でも、実際には専任技術者(専技)が施工現場で管理的仕事をされているのを見ることがあります。
専任技術者(専技)が施工現場で管理的仕事をするには、ある一定の条件を満たした場合にのみ特例として許されることになっています。
2,【特例の条件】
・その専任技術者の属している営業所で契約締結された建設工事であること
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
・営業所と工事現場との間で常時連絡をとりうる体制であること
・専任技術者が所属建設業者様と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
専任技術者(専技)は施工現場で管理的仕事をする技術者ではないことを覚えておかなければなりません。
では、建設業許可の取得後、誰が施工現場で管理的仕事をするのでしょうか。
この役割を担うのが、配置技術者と呼ばれる技術者です。
配置技術者は、➀監理技術者と②主任技術者の2種類に分けることができます。
3,令5年12月22日/技術者制度の概要/国土交通省
配置技術者制度の概要
配置技術者=監理技術者、主任技術者
建設工事の適正な施工の確保
| 工事現場に置く技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 対象工事 |
下請代金総額が4,500万円以上の元請工事 |
下請け工事または左記以外の元請工事 |
| 技術者の要件(概要) |
➀一級国家資格者 ※指定業種=土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種 |
➀一級国家資格者 |
| 特定建設業 | 一般建設業 | |
| 営業所専任技術者の要件 | 監理技術者の要件と同等 | 主任技術者の要件と同等 |
| 許可が必要な工事 |
下請金額が4,500万円以上の元請工事 |
左記以外(軽微な工事を除く) |
|
・建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を設置しなければなりません。 |
||
配置技術者制度は、特定建設業や一般建設業、元請や下請といった建設業者様の違いによって、➀主任技術者と②監理技術者の2種類に分けることができます。
建設業の許可業者は、建設工事の施工現場に配置技術者(主任技術者・監理技術者)を配置しなければならないことをご確認願います。
実は、建設業許可の配置技術者(主任技術者・監理技術者)になるのは、そう簡単ではないのです。
建設業許可の配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、建設業許可の許可要件である専任技術者(専技)と同等の資格や経験を持っている技術者しかなることはできません。
これは何を意味しているのでしょうか?
苦労して時間と手間を掛けて建設業許可を取得しても、専任技術者(専技)になることのできる技術者が社内に2人以上いないと原則として現場施工体制を作ることができないのです。
確かに、特例として、専任技術者(専技)を配置技術者(主任技術者)にできる建設工事もありますが、これはあくまで特例なのです。
工事請負金額によっては、配置技術者(主任技術者)の現場専任を求められる建設工事もあります。
その場合、専任技術者(専技)を配置技術者(主任技術者)にはできず(特例を使えず)、必ずもう一人専任技術者(専技)と同等の資格や経験を持った技術者を必要とします。
【配置技術者の現場専任】
建築一式工事:工事請負代金7,000万円以上の場合に現場専任
建築一式工事以外の工事業種:工事請負代金3,500万円以上の場合に現場専任
建設業許可の取得を希望されている建設業者様は、建設業許可取得後の工事施工体制を考えた技術者の準備をしなければなりません。
建設工事の受注拡大を狙って苦労して建設業許可を取得したのに、配置技術者(主任技術者・監理技術者)の適格者が社内にいないために工事施工体制を作れず、受注できなくなっては余りに残念です。
配置技術者(主任技術者・監理技術者)の確保についても中長期的な視点を踏まえたうえで、配置を考える必要があります。
4,改正 現場技術者の専任合理化
【技術者等の専任義務の合理化】
令和6年12月13日より、技術者等の専任義務の合理化が施行されました。工事現場に専念しなければならないこととされていた監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については、2現場まで兼務できるようになります。
また、
営業所技術者は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については、1現場まで兼務できるようになります。
こちらは法令により施行された内容となりますので、省令で定められる要件については追って発表、施行される予定です。