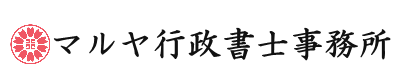建設業許可の取得要件7つ
建設業許可の取得をご検討されているかたは、下記の表にある7つの要件を満たす必要があります。
この➀~⑦の要件が欠けていると許可を取得することはできません。
反対に欠けている場合は、何を満たせば許可がおりるのか目安となりますので参考にしていただければ幸いです。
建設業許可の取得要件7つ
| 7つの要件 | 端的に言うと | 主な要件など | |
|---|---|---|---|
|
建設業許可の取得要件 |
➀誠実性 |
特に心当たりが なければ問題ない |
|
|
②欠格 |
悪いことをしているかどうか |
当てはまれば、許可申請拒否処分 許可後は、許可取消処分も有りうる |
|
|
③財産的基礎 |
一定基準以上のお金を もっている。500万円 |
➀直近の決算書の純資産額 ②銀行の残高証明書 |
|
|
④社会保険 |
加入義務のある国の保険に 加入しているか? |
➀健康保険(法人、個人関係ない) ②厚生年金保険 ③雇用保険(20時間/週の労働時間) |
|
|
⑤営業所 |
請負契約を締結する 自社専用スペースの有無 |
自社のみで占有できるスペースが必要 |
|
|
⑥専任技術者 |
許可を取りたい業種の 技術部門の責任者の配置 |
➀10年以上の工事の実務経験 ②指定学科+実務経験 3~5年以上 ③国家資格 検定試験合格者 ➀~③いずれか満たす |
|
|
⑦経管 (経営業務管理責任者) |
建設業の経営のプロが いるかどうか |
➀専属であること ②5年以上建設業の経営経験 |
➀誠実性
・誠実性がないと判断される定義
1,建設の請負契約時に、詐欺や横領、請負契約を違反する行為が明らかな者
2,客観的に明らかに不正又は不誠実である行為をする建設業者だと申請書だけで役所が判断することは難しい為、特に心当たりがなければ問題ないと思います。
・誠実性がみられる対象
1,法人 ⇒役員全員
2,個人事業主⇒本人
②欠格
簡単に言えば、今まで悪いことをしていなかったかどうかと言うことになります。
「欠格要件の対象になるかた」ですが、
1,法人であれば役員全員
2,個人事業主であれば本人
が対象となり、反対解釈すれば法人、個人事業主に雇われている者が欠格要件に該当しても許可を受けるうえで問題となることはありません。
欠格要件の確認内容
1,自己破産したことはあるか?
2,昔、建設業許可を取消された心当たりはあるか?
3,昔、建設業の営業停止処分を受けた心当たりはあるか?
5,禁固刑、罰金刑、懲役刑を受けたことはあるか?
6,未成年者か?
7,暴力団と関係あるか?
8,精神的な障害があると診断された経験はあるか?
以上の1,~8,に「欠格要件の対象になるかた」が該当しなければ、欠格要件を満たしていると言うことになります。
仮に該当している場合は、その内容につき、精査することが必要となります。
私自身から細かくうかがうことには正直気が引けるのですが、一定の期間が経過していることにより、欠格要件が満たされることもありますので詳しくおうかがいしています。
また、非常に重要なことなのですが、欠格要件を満たしていることは、許可申請書提出時のみならず、許可取得後も常時満たしている必要があります。仮に、許可取得後、欠格要件に該当する事態に陥った場合、許可が取り消されることがあります。
③財産的基礎
簡単に言えば、「一定基準以上のお金を持っていないと許可はあげません」と言うことです。
この一定基準とは500万円です。
500万円以上の金額を持っていることの証明が必要となりますが証明する方法として2つの証明方法があります。
1,直近の決算日の貸借対照表
2,銀行の預金残高証明書
となります。
1,直近の決算日の貸借対照表
すでに決算を迎えている事業者は手元に決算書があります。一番最近、税務署に提出した決算書を開くと、「貸借対照表」と書かれた書類がありますので、「貸借対照表」の「純資産の部」にある「純資産合計」にある額をご確認ください。500万円以上の額が記載されていれば、財産的要件は満たしています。
仮に満たしていない場合、銀行の預金残高が500万円以上あれば財産的基礎を満たしています。
2,銀行の預金残高証明書
銀行の預金残高が500万円以上あれば財産的基礎を満たしています。
残高証明書の注意点
審査機関にもよりますが、申請書が受理される1ヶ月以内が有効期限となります。
④社会保険
建設業許可制度で言う社会保険とは次の3つを指します。
1,健康保険
2,厚生年金保険
3,雇用保険
この1,~3,に加入義務のある事業者は適切に加入していなければ、建設業許可を取得することは出来ません。
加入義務のある事業者とは、
1,健康保険
➀自治体が管轄する国民健康保険
②国民健康保険組合(土建国保、建設国保など)
③全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)
④健康保険組合
となります。
表にすると下記の通りとなります。
| 保険の種類 | 適切性 | ||
| 法人 | 個人事業主 |
5人以上雇用する |
|
|
➀自治体が管轄する |
✖ | ◯ | ✖ |
|
②国民健康保険組合 |
◯ | ◯ | ◯ |
|
③全国健康保険協会 |
◯ | ━ | ◯ |
|
④健康保険組合 |
◯ | ━ | ◯ |
◯=加入義務あり
2,厚生年金保険
| 厚生年金保険加入義務者 | 適切性 |
|
法人 |
◯ |
|
個人事業主 |
✖ |
|
5人以上雇用している個人事業主 |
◯ |
◯=加入義務あり
3,雇用保険
法人/個人は関係ありません。
週に20時間以上働く労働者がいるかどうかで加入義務の有無が決まります。
| 雇用保険加入義務者 | 適切性 | |
| 法人 | 個人 | |
|
20時間/週未満働く労働者 |
✖ | ✖ |
|
20時間/週以上働く労働者 |
◯ | ◯ |
◯=加入義務あり
つまり、
・取締役しかいない法人
・週に20時間未満働くアルバイトのみ雇用している
場合は雇用保険への加入義務はありません。
⑤営業所
建設業法上、営業所では建設工事の請負契約を締結することが想定されています。
つまり、顧客を招き入れることができる➀接客スペースと②事業専用スペースを有することが前提となりますので、
➀②の要件を満たす営業所が必要となります。
例えば、営業所を借りている場合、
要件を満たすと判断できる場合
一つの部屋を自社と他社で借りている場合、入り口は共用で同じ入り口を使用しているが、部屋自体が明確に区分されているとします。
この場合は自社の専用スペースがあると判断されます。
要件を満たさないと判断される場合
比較的大きな部屋に複数の会社が事務所を構え、自由に出入りできるコアワーキングスペースと呼ばれるもの。
専用デスクがあったとしても建設業法上の営業所として認められない可能性が高いです。
なぜなら、➀②の要件を満たしているとは言えないからです。
このような仕様の場所を営業所として現在使用している場合は、自社で占有できるプライバシーが確保された営業所を探すことが望ましいと言えます。
ほかの注意点
・固定電話番号がある
・社名の標識を掲げている
・事務スペースがある
・郵便物が届く
・自宅を営業所にする場合は居住スペースと明確に区分する
⑥専任技術者
建設業許可を取得するための重要なステップとして「自社で取得すべき業種を特定すること」が挙げられます。
例えば、
「電気通信工事業」の営業許可を取得したい場合で、専任技術者の要件を検討します。
1,500万円以上の電気工事を請負いたい場合、建設業「電気通信工事業」の許可が必要となります。
2,電気通信工事に詳しい知識と経験が豊富な技術者が在籍している事業所だと許可行政庁からお墨付きを受ける必要があります。
↑
この技術者のことを専任技術者と言います。
専任技術者は一社に専属でなければなりません。
他の会社で専任技術者として登録されている人を雇っても自社の専任技術者として登録することはできません。
具体的に専任技術者となるための要件をご説明しますと、
➀実務経験10年以上
②指定学科卒業+一定以上の実務経験
③有資格者
この➀~③のいずれかの条件を満たすことが求められています。
まとめたものが下表になります。
| 専任技術者の要件 |
「申請業種に対応する技術的専門性を有していることの証明」 ➀実務経験10年以上 ②指定学科卒業+一定以上の実務経験 ③有資格者であること ➀~③のいずれかを満たしていること |
|
「雇用形態」 ②常勤の役員に就任している |
⑦経管(経営業務の管理責任者)
通称:経管(ケイカン)についてのご説明をします。
分かりやすく言うと、建設業の経営のプロである責任者です。建設業許可を取得すると、大きな工事の受注が可能となります。
このため、建設業の経営経験が全くない人が経営している会社だと不安になります。
経管(経営業務管理主任者)の要件
➀一定期間以上、建設工事を請負う会社の取締役の経験を持つ者を専属にしておく。
または、
②一定期間以上、建設工事を請負った個人事業主の経験がある者を専属にしておく。
を要件としています。
経営者なので役員である必要があり、専属なので一社でしか経管になることはできません。
➀②にある一定期間以上とは5年以上を指しますので経管になる者は5年以上の建設業の、役員の経験または、個人事業主としての
経験が必要となります。